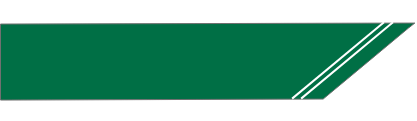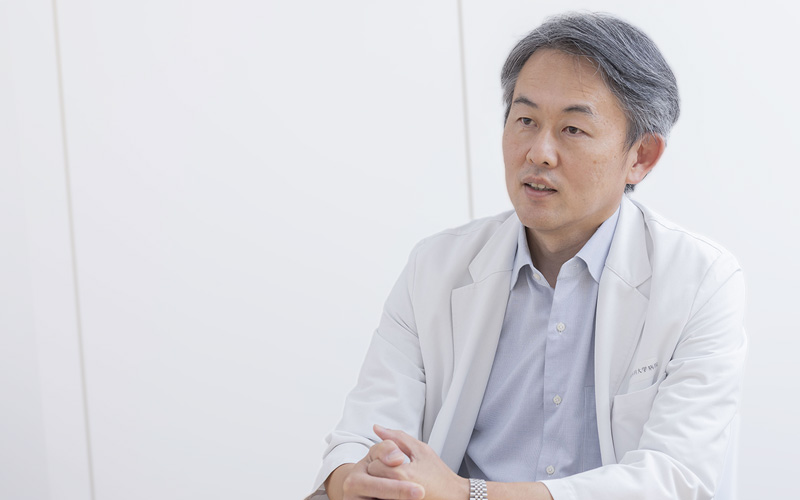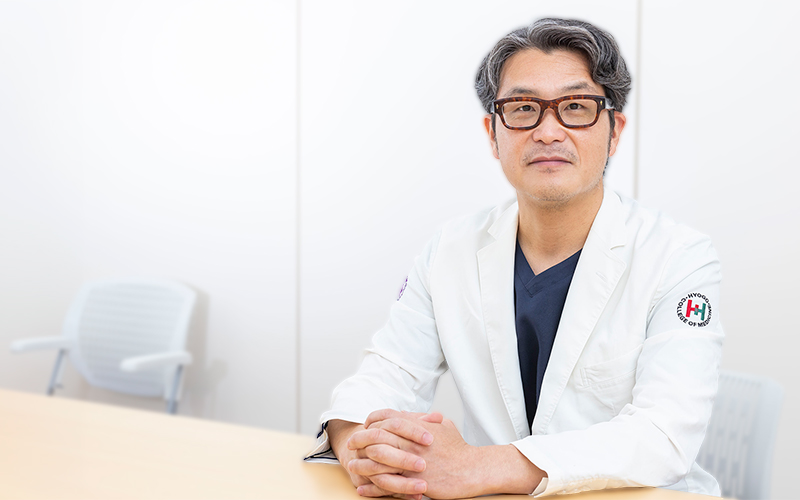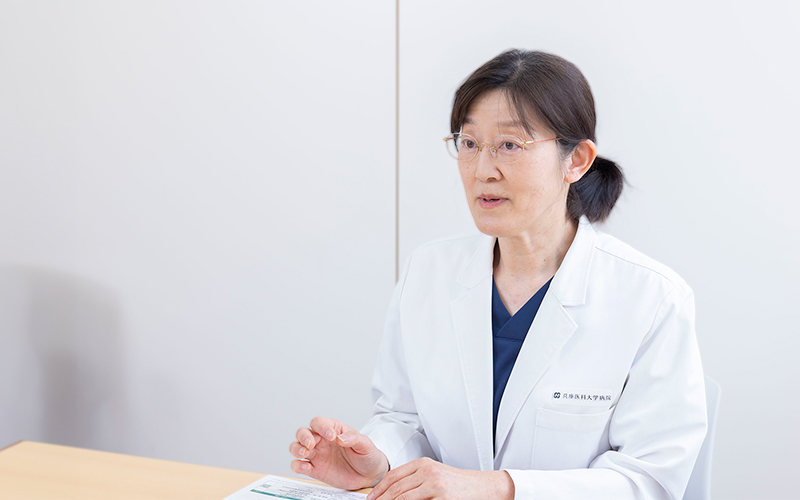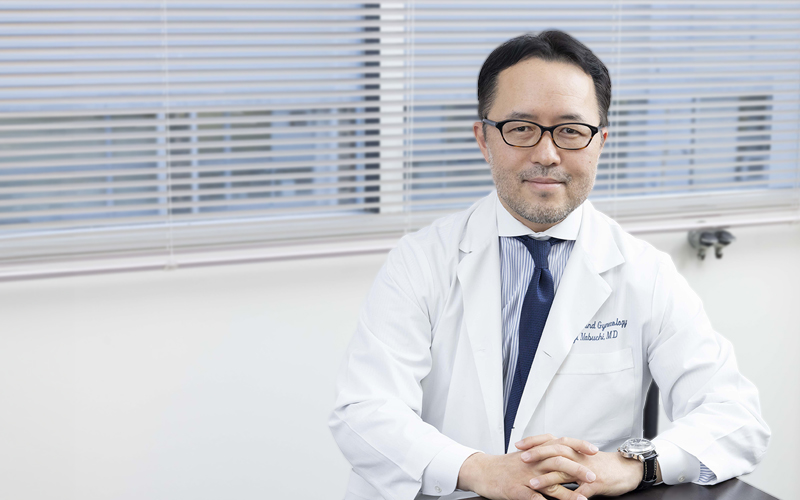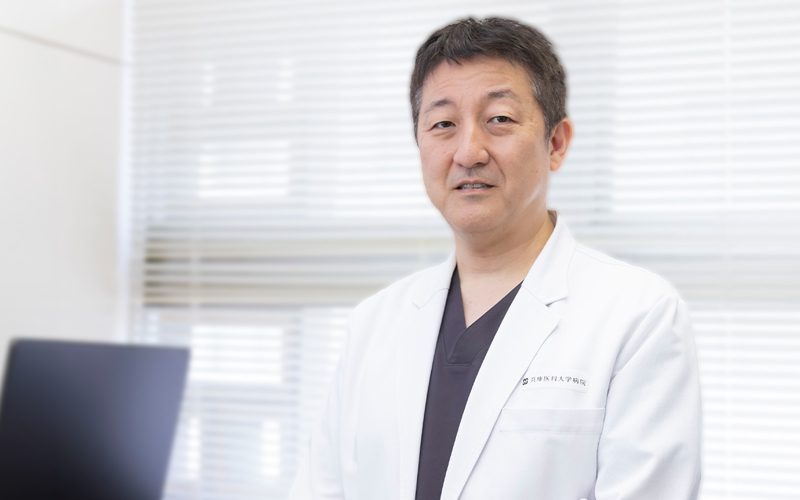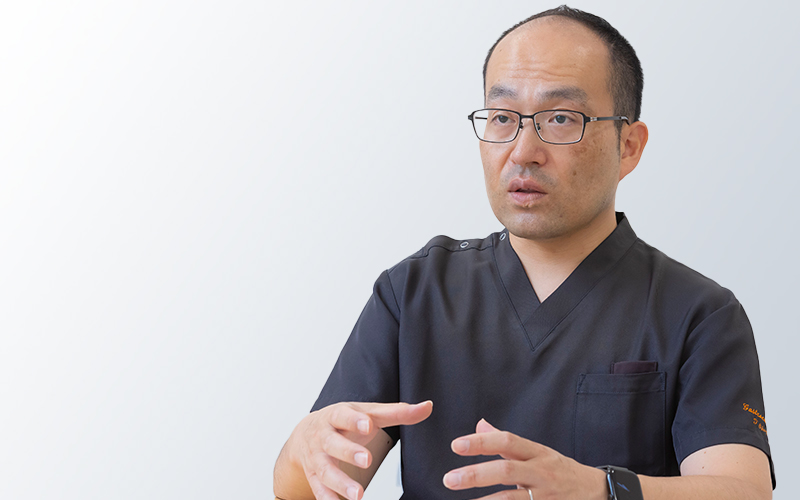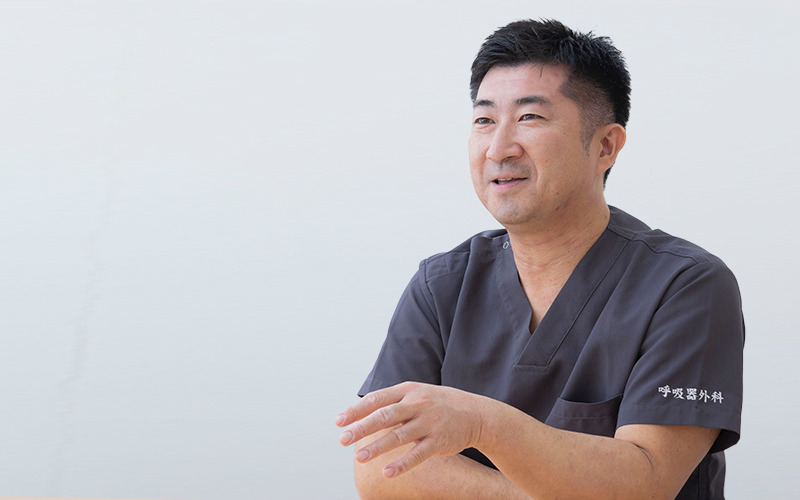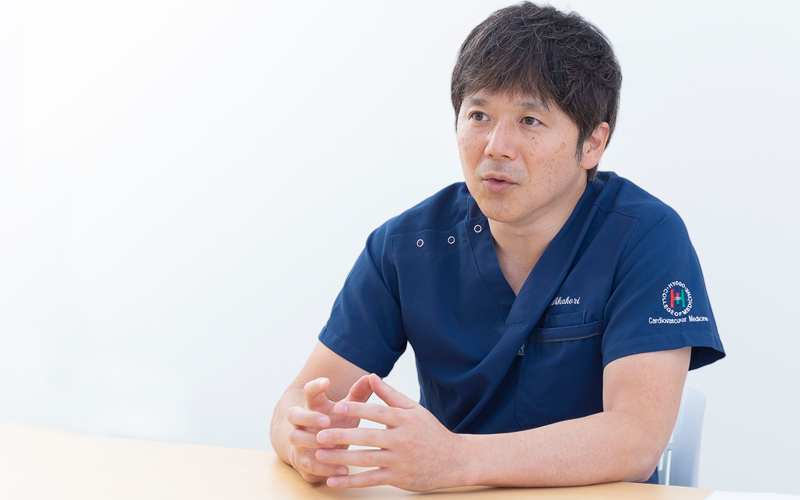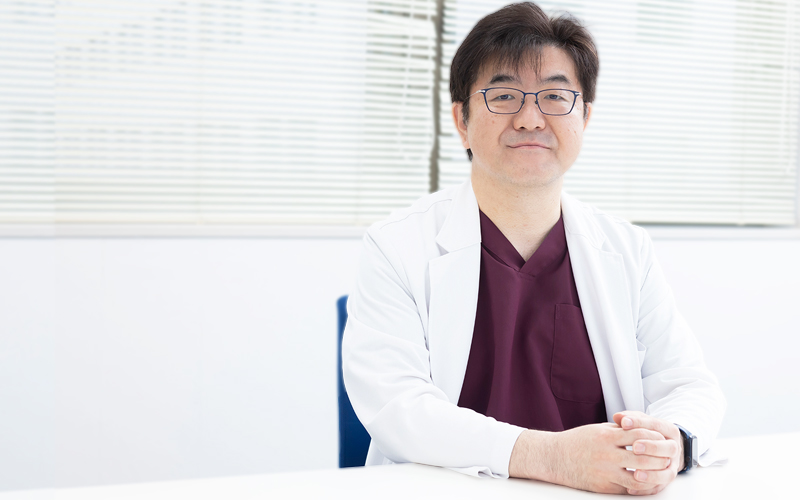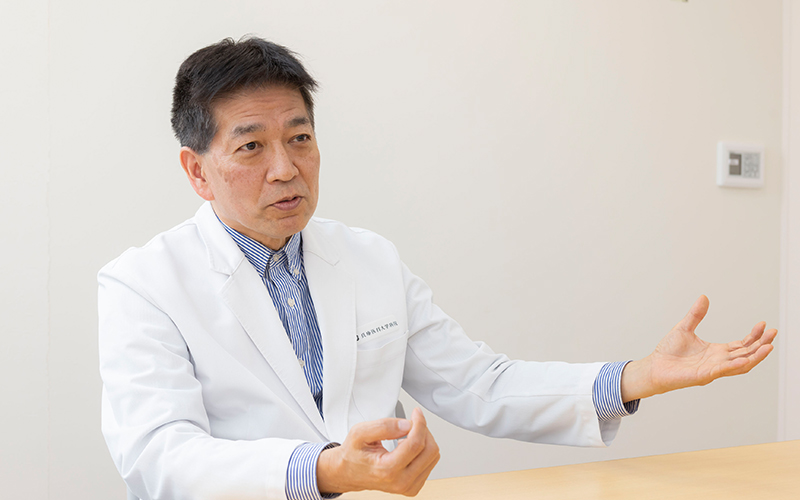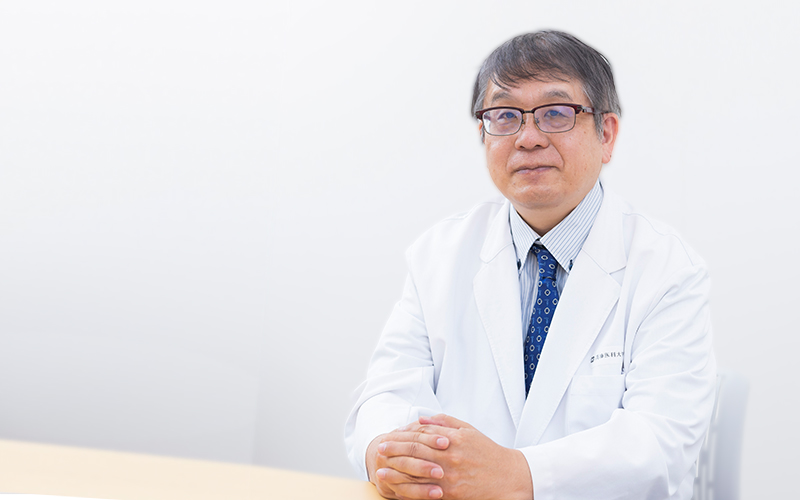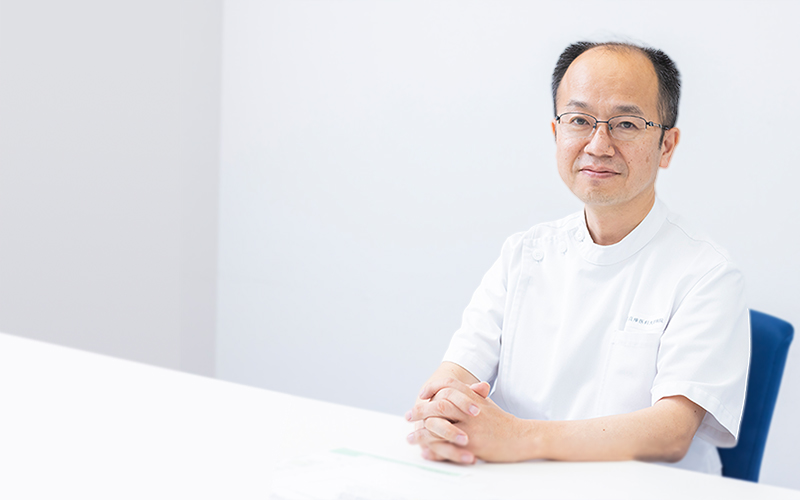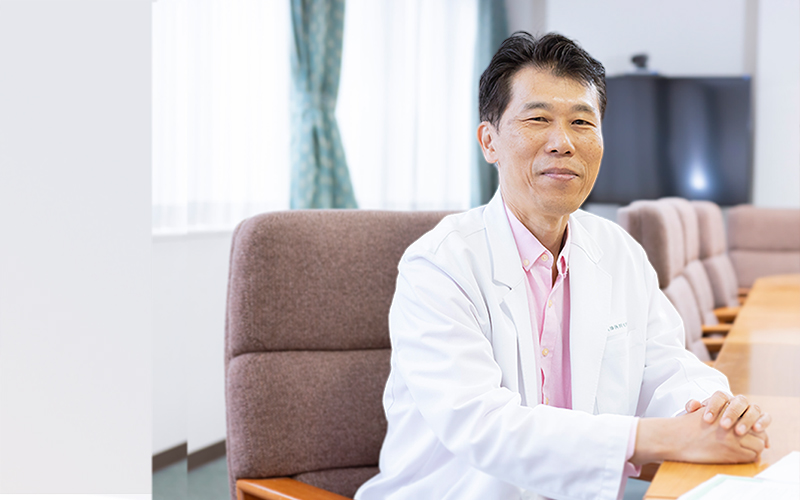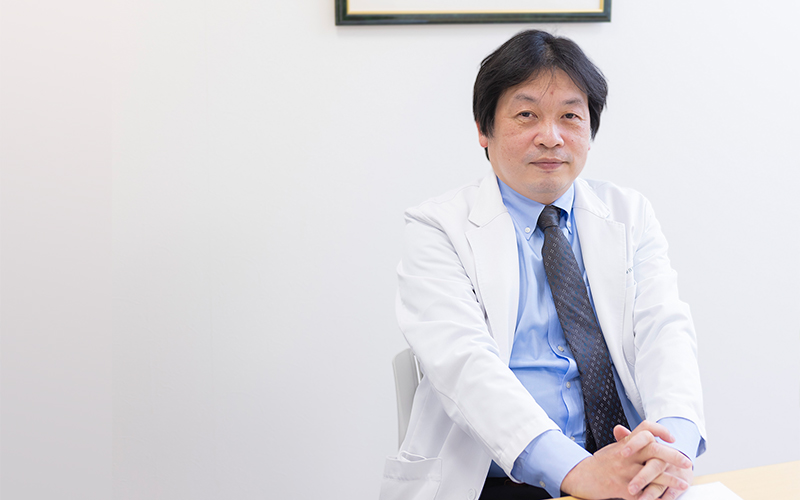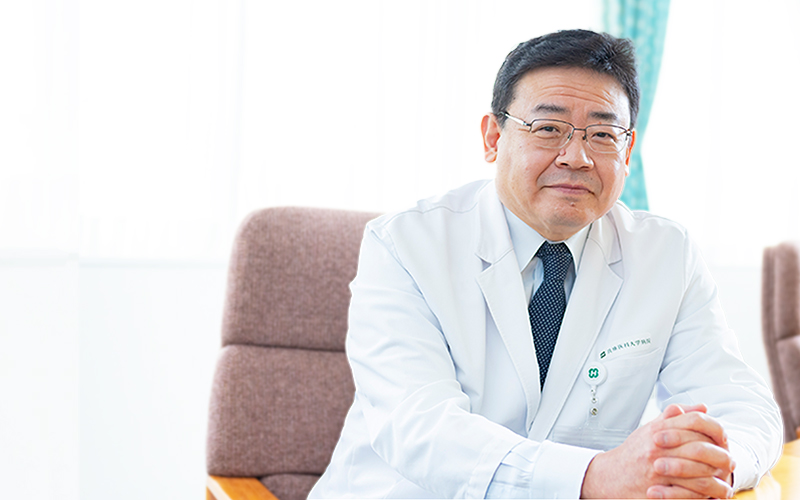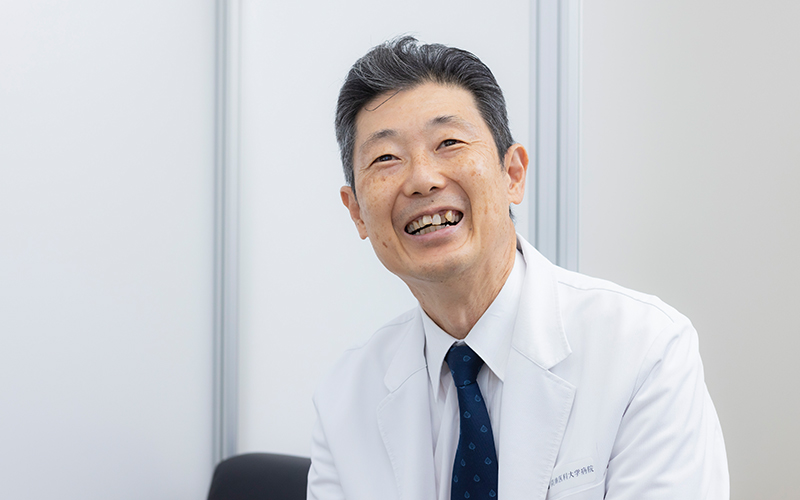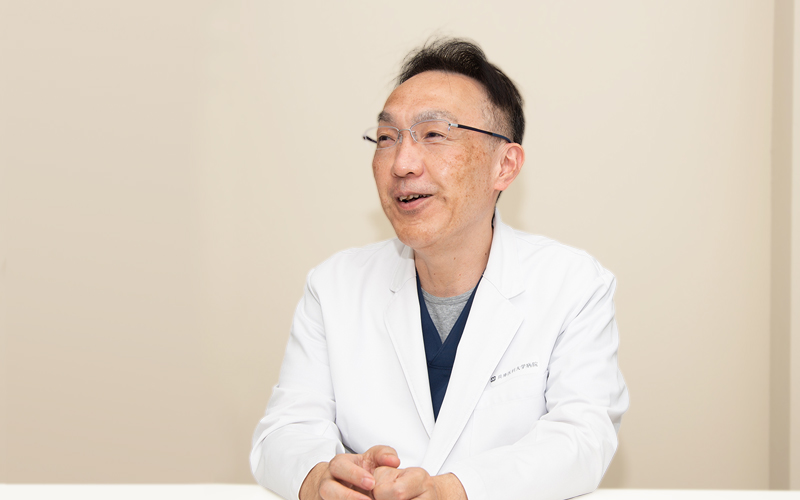長引く咳嗽は確実な診断・治療が重要
長引く咳嗽は、呼吸器内科に外来受診される患者さんで最も多く見られる主訴です。咳嗽は発症からの期間によって、急性(3週間未満)・遷延性(3週間~8週間)・慢性(8週間以上)に分けられますが、遷延性咳嗽や慢性咳嗽では感染症以外の原因が多くを占めます。原因として日本人で特に多いのは気管支喘息や咳喘息で、この診断と治療を確実に行うことは非常に重要です。
喘息において、診断の最も重要な手がかりとなるのは問診です。日内変動がどれくらいあるか、温度差や季節の影響はあるか、花粉症やハウスダストといったアレルギー素因はあるか、横になったときなど姿勢による症状の変化はあるか、既往歴や家族歴も含めて細かく問診をしていく必要があります。また、当院では呼気ガス検査も行い、一酸化窒素の濃度を測定して診断を行っています。
生物学的製剤により格段に進歩した慢性期治療
喘息の重症度は、軽症間欠型・軽症持続型・中等症持続型・重症持続型の4つのステップに分類されており、そのステップに応じた治療方針があります。正しい診断・治療が行われていれば、喘息の症状は2週間ほどで快方へと向かっていきます。そうでない場合は、本当に診断が正しいのか、何か合併症が隠れていないか、あるいは薬の量や吸入方法などが適切かどうか、といったポイントについて一度立ち止まってチェックする必要があります。
これらを確認した上で、それでもなかなか症状が安定しない場合は、近年は難治性喘息の新たな治療法として、生物学的製剤が登場しています。生物学的製剤は喘息症状を引き起こす原因物質に対してピンポイントで治療できるため、目覚ましい回復が期待できます。また、従来のステロイドによる治療よりも圧倒的に副作用が少ないのが特徴です。生物学的製剤を治療に取り入れる場合は、2週間あるいは1ヶ月に1度くらいのペースで効果を見ながら、3ヶ月ほど試してみて、徐々にステロイドの量を減らしていくケースが多いです。
病診連携のもとで継続的な喘息治療を
喘息発作が起きてしまったときは、発作の程度に応じてβ2刺激薬やステロイドを用いた治療を行います。苦しくて横になることができないような中等度の発作(中発作)のときは、全身のステロイド投与が必要になるため、地域の病院やクリニックでの対応が難しい場合は当院にご紹介いただくケースもあります。
あるいは、前述のように2週間以上治療を続けているにもかかわらず症状が安定しない場合でも、当院にご紹介いただければ、合併症や薬のチェック、画像検査などを行い、改めて診断を行います。必要であれば当院で治療をして、症状が安定したら地域の先生のもとに戻って治療を継続していただくといった形で、病診連携も密に行っています。


地域と連携し、これからも幅広い呼吸器疾患に対応
当科では、地域の医療機関とのより良い協力体制を築くため、呼吸器疾患を扱っている近隣の病院やクリニックを対象に、アンケート調査を実施しています。例えば「診断がついていれば経過観察はできる」、あるいは「経過観察は可能だけれど治療の対応は難しい」など、どの疾患をどの程度まで診療可能なのか、各施設の状況をアンケートで把握しておくことで、より円滑な連携を行うことができます。当科の祢木芳樹先生が中心となって進めているこの「阪神呼構想(はんしんここうそう)」という連携体制を、今後もさらに推進していきたいと考えています。
大学病院の呼吸器内科は、がんの患者さんが多いという印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、当院では生物学的製剤の導入にも早期から取り組み、がんだけではなく一般呼吸器疾患も幅広く扱っていますので、ぜひ気軽にご相談いただければと思います。
Doctor's Profile

みなみ としゆき
南 俊行
呼吸器内科
准教授
- 専門分野
-
- 呼吸器内科
- 肺癌・中皮腫
- 癌化学療法
- 資格
-
- 日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医
- 日本呼吸器学会専門医・指導医・代議員
- 医学博士(2012年)
過去に開催された「兵医サタデーモーニングセミナー」のアーカイブ動画は、兵庫医科大学病院の登録医制度「武庫川クラブ」にご登録済みの先生方、 および一部の関連医療機関の先生方のみ視聴可能なコンテンツです。上記のインタビュー記事を読んで「アーカイブ動画を視聴したい」と思った方は、武庫川クラブへのご登録をお願いします。
武庫川クラブ(登録医制度)へのご登録はこちらから