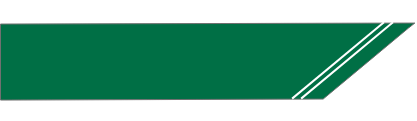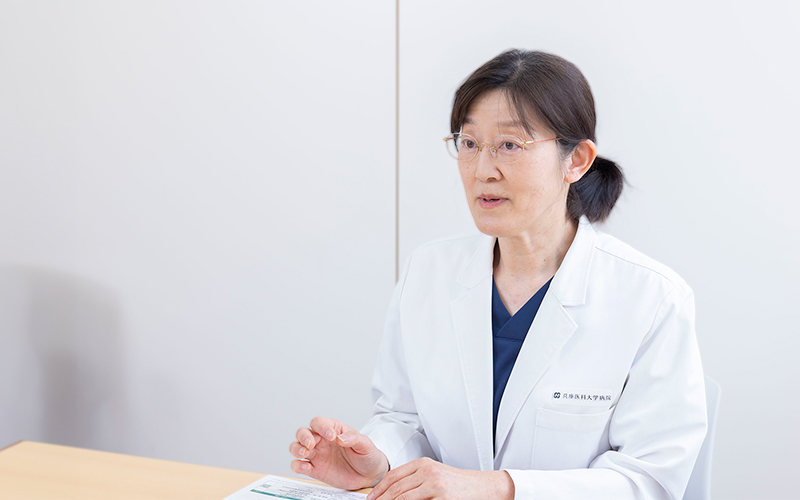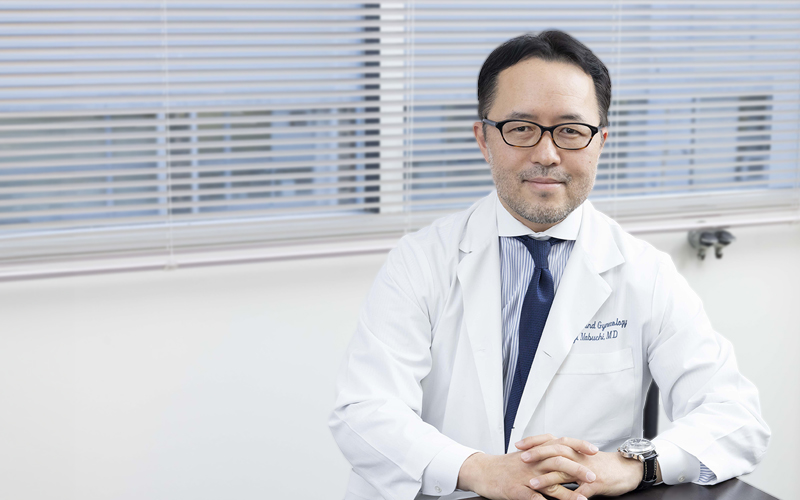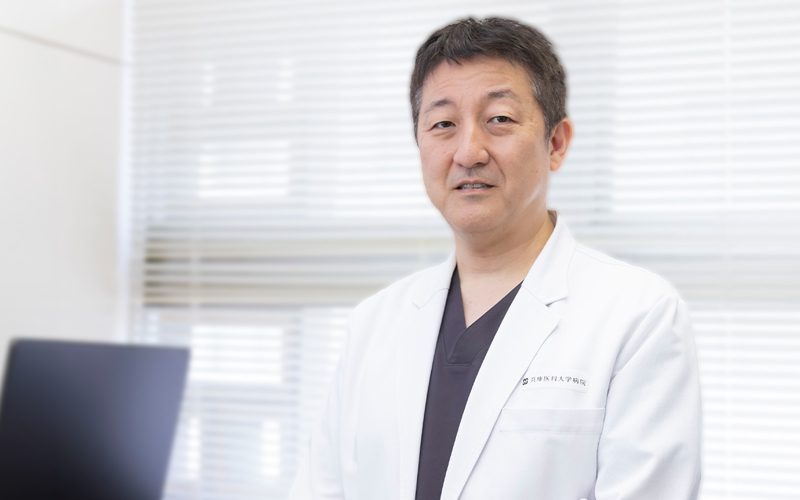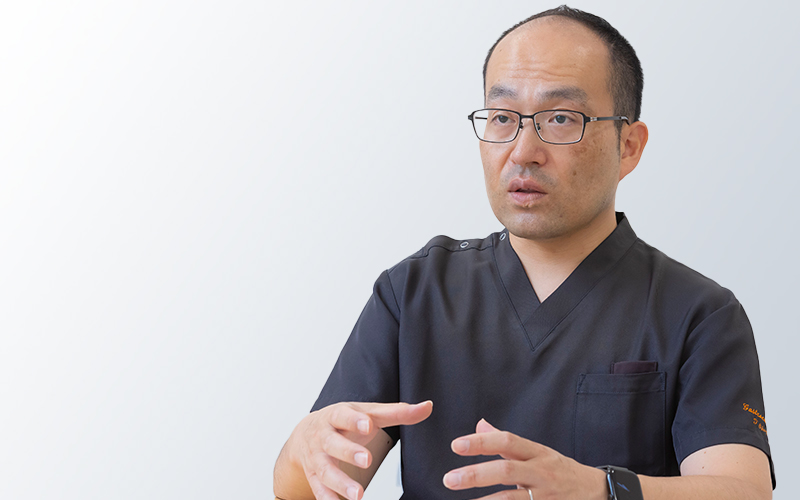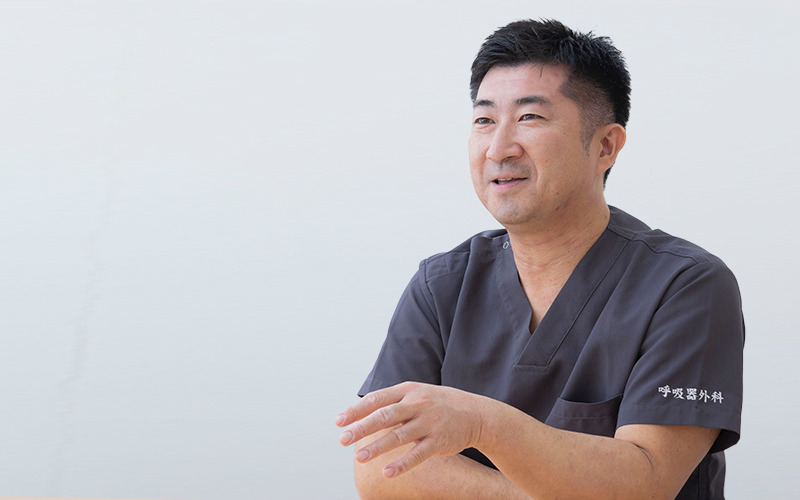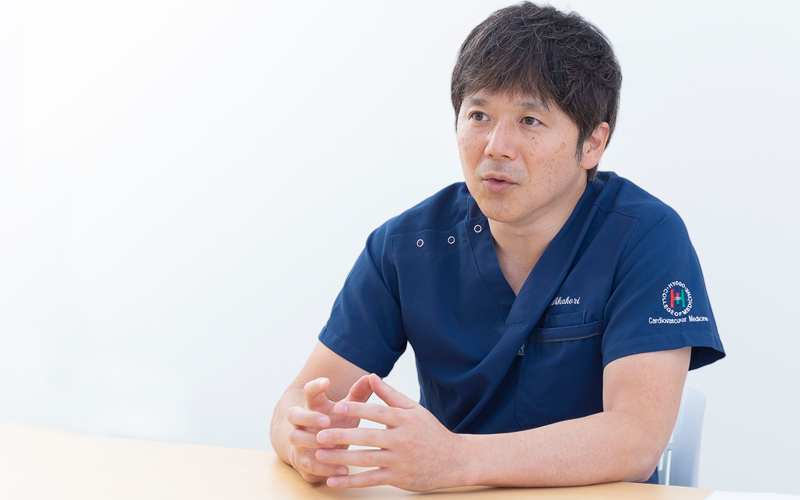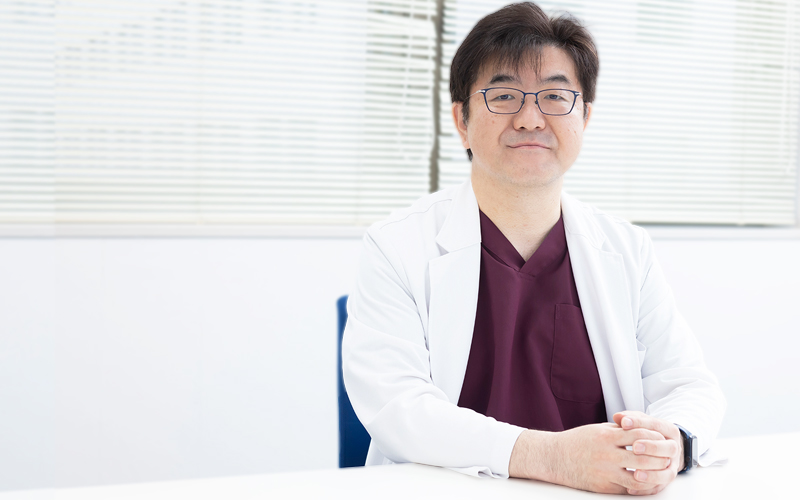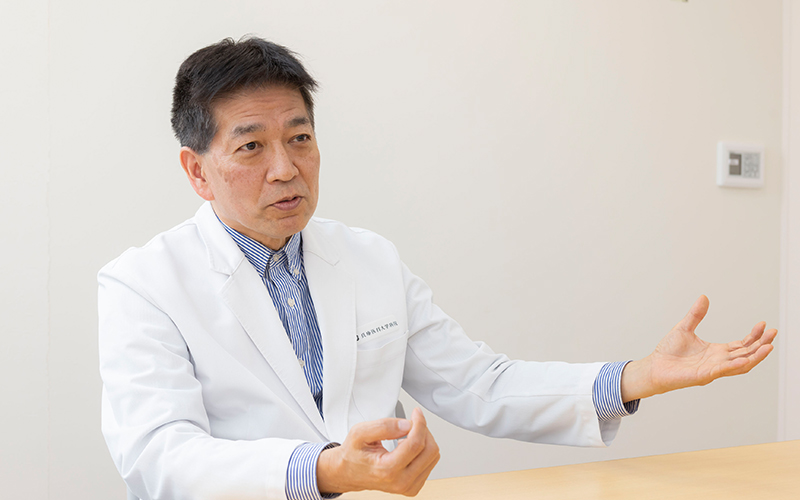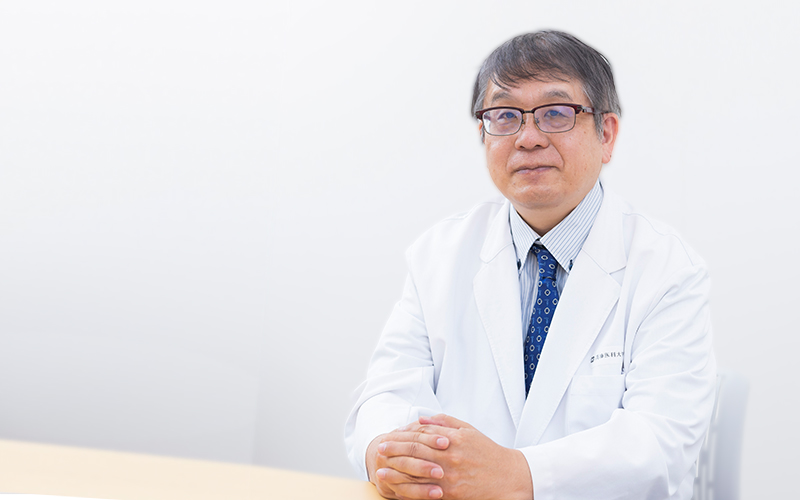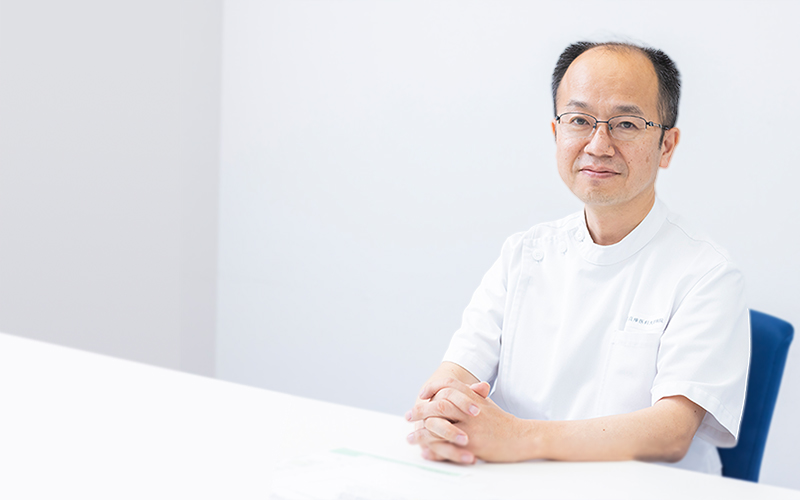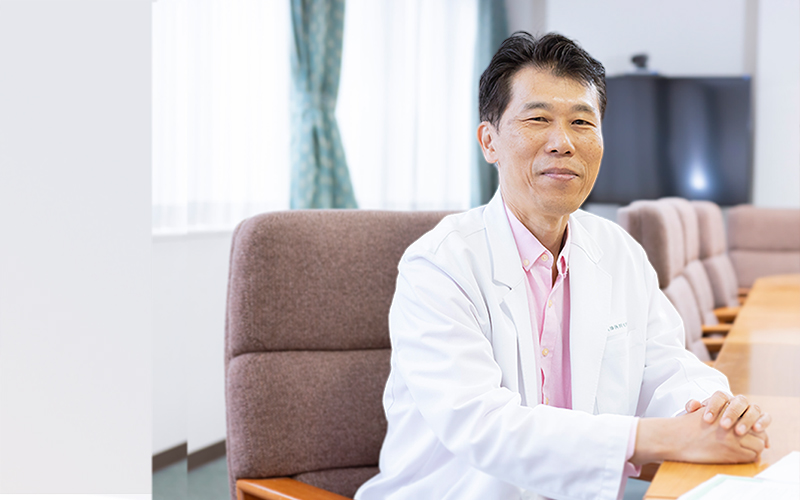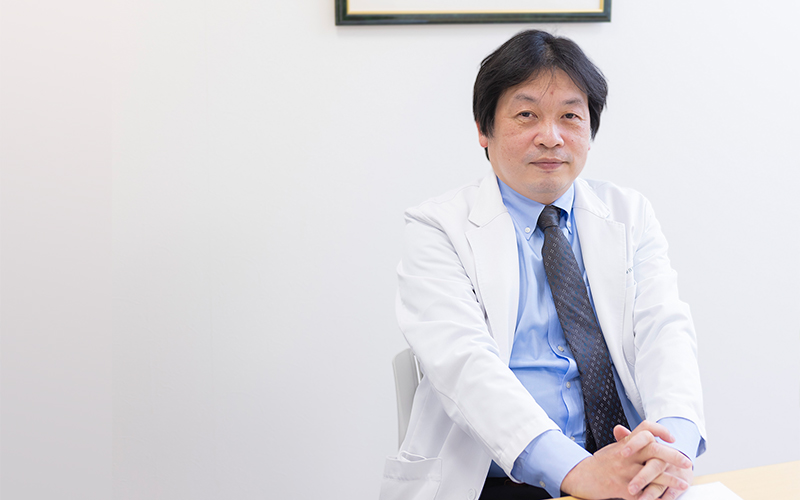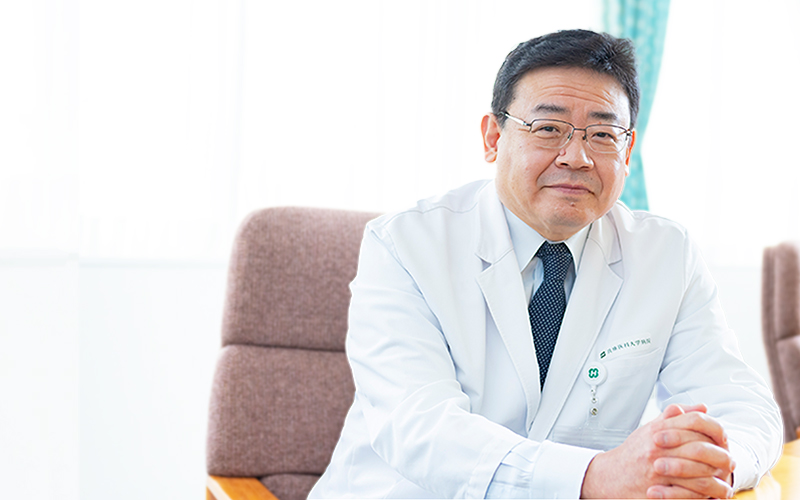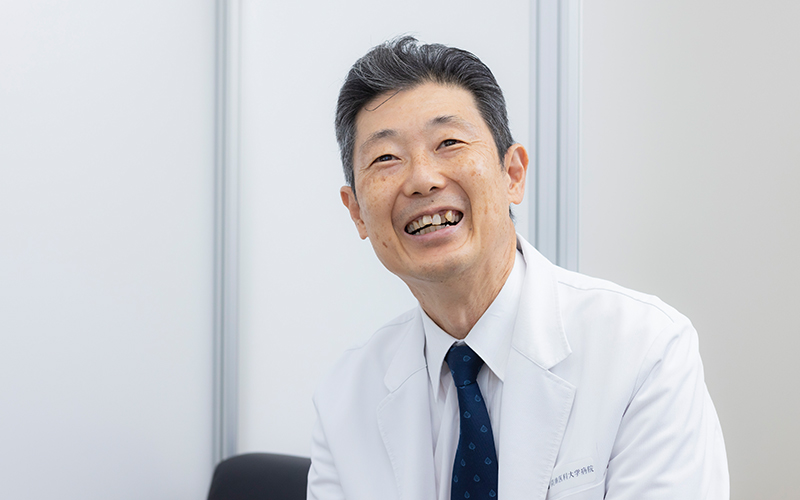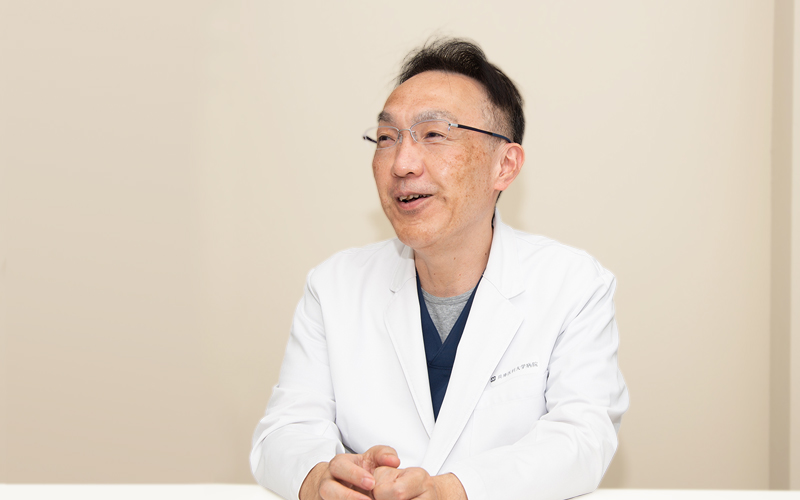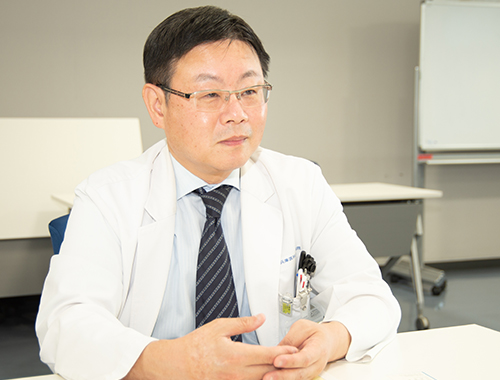
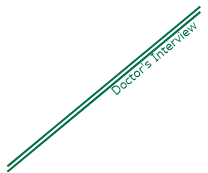
潰瘍性大腸炎とは
潰瘍性大腸炎は国が指定する難病、特定疾患の中で最も患者数の多い病気です。もともとアメリカで症例が多かったのですが、日本でも急増しており、現在およそ22万人を超えて米国に次ぐ世界2位の患者数になっています。
症状としては下痢や粘血便、腹痛などがあります。大腸に炎症や潰瘍ができ、そこから血液や蛋白が漏出することで起こります。腸は本来、便と、無菌の体内との境目、バリアの役目をしているのですが、潰瘍ができることでこのバリアが壊れて、体内の栄養分や血が流れ出てしまいます。さらに重症になってくると、逆に便の中の細菌などが体内に侵入してくることもあります。高熱が出て、抗生物質を使わなければならない場合もあります。
根本的な原因はまだ特定されていません
この病気の根本的な原因はまだすべて解明されていません。欧米で特定された発症に関する遺伝子の変異が日本人の患者さんでは当てはまらなかったりしますし、いわゆる遺伝病ではありません。
他の原因としては「食生活の欧米化」などが言われていますが、もうひとつ言われているのが「衛生化説」、不衛生な状態から衛生的な状態になるとだんだん増えてくる、というものです。その国の水洗トイレが増えると患者数が増えてくるとも言われていますが、原因なのか結果なのか、因果関係はわかっていません。遺伝的要因、環境の要因、食事の要因、いろんなものが合わさって発症してくると考えられています。
内科的な治療と
外科的な治療があります
20年、30年前には、内科的な治療に今ほど多くの選択肢が無く、内科的な治療の限界イコール外科手術、それはもう、命を救うための選択でした。中途半端に炎症のあるところを残すとそこでまた再発しますから、炎症が起こっている場所だけでなく大腸を全て取ってしまう、大腸全摘術ということになります。この手術で一番多く行われている術式を考案したのが、兵庫医科大学の先代教授である宇都宮教授です。
内科の治療に使う薬はこの数年、毎年のように新しいものが出てきています。それによって従来だったら入院が必要な患者さんが外来で済むとか、入院しても外科手術に至らないというようなことも増えてきました。
内科的な治療で目指すところは
この病気は慢性の病気なので、良くなったり悪くなったり、増悪と寛解を繰り返すことが多く、治療としてはこの寛解期をできるだけ長くして再発を抑えるという方針で進められます。良くなったら治療は終わりではなくて、悪くならないように保つ治療が必要です。ただこのとき、「粘血便が出ない」とか「お腹が痛くない」とか、そういうところを目標にしてしまうと、その時点ではまだ内視鏡で見ると潰瘍が治りきっていない、症状が自覚できない程度に炎症が軽減しただけ、ということもよくあります。こういうレベルを治療目標としてしまうと、再燃や将来の発がんのリスクが高くなるので、今は内視鏡で見ても潰瘍が治っているというレベルを目標に治療します。いろんな薬ができたので、それが達成できる確率が以前より高くなっています。
内科的治療の
選択肢が多くなりました
種類としても、働き方としても様々な新しい薬がたくさん出てきたことで、内科治療の選択肢も増えました。たとえば昨年は4つくらい新しい薬が出ましたし、これからも新しいものがさらに出てきます。
この病気の特徴として、症状や治療効果に個人差が大きく、医師も対処に経験を要します。兵庫医科大学は患者さんが多く集まりますから、医師の経験も豊富で、新しい薬を使用する経験も多いです。その意味で、私たちは「潰瘍性大腸炎と戦う最後の砦」という自覚を持って、日々の診療に従事しています。
Doctor's Profile
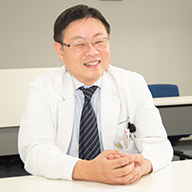
わたなべ けんじ
渡辺 憲治
消化管内科
准教授
- 専門分野
-
- 炎症性腸疾患の病態・診断・治療
- 大腸腫瘍性病変の内視鏡的診断と治療
- 小腸疾患の病態・診断・治療
- 小腸内視鏡(カプセル内視鏡、バルーン内視鏡)
- 資格
-
- 日本消化器病学会 専門医・指導医
- 日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
- 日本内科学会 認定医
- 日本消化管学会 胃腸科認定医・胃腸科指導医
- 日本大腸肛門病学会 専門医・指導医
- 日本カプセル内視鏡学会 専門医・指導医
- 医学博士(1999年)
過去に開催された「兵医サタデーモーニングセミナー」のアーカイブ動画は、兵庫医科大学病院の登録医制度「武庫川クラブ」にご登録済みの先生方、 および一部の関連医療機関の先生方のみ視聴可能なコンテンツです。上記のインタビュー記事を読んで「アーカイブ動画を視聴したい」と思った方は、武庫川クラブへのご登録をお願いします。
武庫川クラブ(登録医制度)へのご登録はこちらから