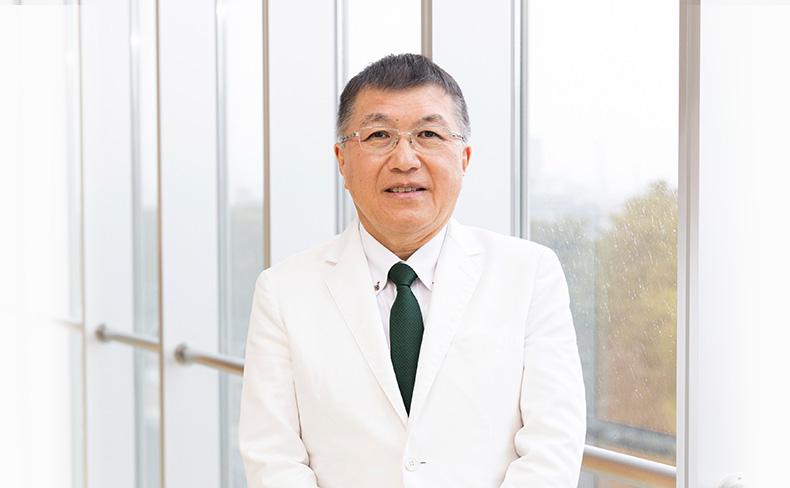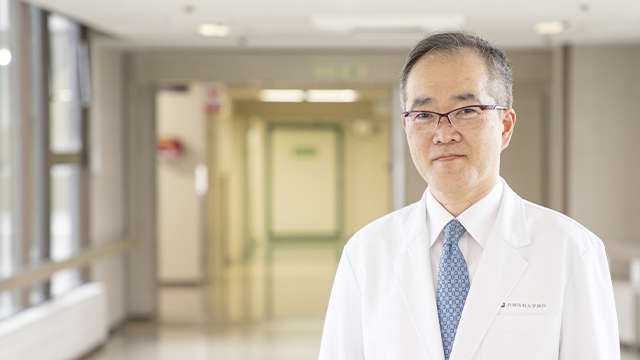今日の医療に必須な「チーム医療」
「チーム医療」とは、「医師をはじめとするメディカルスタッフ(医療専門職)が、患者さんと共に、それぞれの専門性をもとに、高い知識と技術を発揮し、互いに理解し目的と情報を共有して、連携・補完しあい、その人らしい生活を実現するための医療」と定義されています。チーム医療として以前から実践されてきたものに「栄養サポートチーム(NST)」があります。1970年代から欧米に普及し始め、1990年後半からわが国にも導入されるようになりました。日本でも、2009年8月、厚生労働省が「チーム医療の推進に関する検討会」を立ち上げ、日本の実情に即した医師と看護師等との協働・連携の在り方を検討し始めました。それ以降、本邦でもチーム医療の概念が急速に普及しました。
兵庫医科大学病院では、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、そして医療ソーシャルワーカーや事務職員まで、医療に携わる多職種が連携したチーム医療で質の高い診療ができるよう心がけています。
チーム医療を発揮できる独自の背景
チーム医療では医師と医療スタッフが同じレベルに立っていることが重要です。上下関係がなく、お互いの専門分野を尊重し協力し合う「輪」のような関係性です。当院は伝統的に職種間の壁が低く、互いに意見を言いやすい職場風土があったため、チーム医療が根付きやすかったのかもしれません。
兵庫医科大学は設立50周年時に、同一法人内の兵庫医療大学と統合し、医学部、薬学部、看護学部、リハビリテーション学部を有する医療系総合大学として新しい歩みを始めました。各学部の学生は1年次からチーム医療について学んでおり、医師や医療職をめざす学生同士で症例を用いた実践的な実習も行っています。学生時代に高い専門性とコミュニケーション能力を身につけた人材が多く入職してくることもあり、当院ではチーム医療がスムーズに実現できているように思います。
スムーズな連携が患者さんのストレスを軽減する
チーム医療の導入によって、特に入院・退院が非常に円滑になりました。
例えば入院では、患者さんはまず医療支援センターで職員から入院についての説明を受けます。その後、薬剤師が薬剤処方の全履歴を調べて服薬指導を行い、看護師が入院生活や治療について説明し、技師が検査結果を医師に報告し、医師が治療計画を立てていきます。つまり多職種が「輪」のようにつながって一人の患者さんを迎え入れる体制ができているのです。
患者さんに関するすべての情報は、専用の電子カルテで共有されています。治療経過や服用薬剤をはじめ、これまでの薬剤処方履歴、アレルギーの有無、食事や生活で気をつけないといけないことなど、重要な情報は電子カルテのトップに赤文字で目立つように記すようにしています。そのため、もし主治医に直接言いにくいことがあっても看護師に伝えたり、リハビリの場で言いそびれたことがあっても後で他スタッフに言ったりしておけば、基本的にはその患者さんに携わる全職種が情報を共有できるようになっています。患者さんにとっては、何度も説明していただいたり不安に感じたりするストレスが軽減し、安心して治療に専念できる助けになっているのではないかと思います。このチーム医療体制は退院後のフォローアップでも力を発揮しています。
チーム医療は文字通りチームで対応するため、患者さんやご家族の疑問にも迅速かつ的確にお答えすることができます。各職種の専門性を生かし、柔軟な対応ができるように病院全体で努めています。
急性期におけるチーム医療とは
兵庫医科大学病院には、多職種が所属部署を越えて活動している18の医療チームがあります。その中でも、急性期医療では「感染制御部 感染対策チーム(ICT)」、「栄養サポートチーム(NST)」、「呼吸ケアチーム(RST)」が介入するケースが多いです。
「感染対策チーム」は、医師や看護師、薬剤師、臨床検査技師で構成されており、院内感染予防や耐性菌対策を行っています。ここ数年間のコロナ渦において、感染対策チームの活動は目覚ましいものがありました。「栄養サポートチーム」には管理栄養士や言語聴覚士などが参加し、定期的に病棟を回診して入院患者さんの栄養管理を担当しています。「呼吸ケアチーム」は、集中治療医や救急看護認定看護師、歯科医や歯科衛生士などが参加し、人工呼吸器装着患者さんや呼吸管理に問題を抱えている患者さんの回診を行っています。もちろんチーム単体で完結するわけではなく、回診の調整がつけば合同カンファレンスができるように調整し、それ以外の時は電子カルテを通じて連携しています。
回復期におけるチーム医療とは
骨折のような整形外科疾患ではリハビリテーションセンターが中心となって手術後の早い段階から患者さんに関わっています。理学療法士が病棟まで出向いてベッドの上でリハビリを行い、病棟看護師と情報交換を行います。患者さんをチームで支えることで、手術直後の状態を把握し、早い段階からのリハビリで経過を良くできるメリットがあります。
オーラルケア(口腔ケア)にもチームで取り組んでいます。オーラルケアは手術後の肺炎や感染症を防ぐためにとても有効なため、手術前の患者さんのもとに歯科医師と歯科衛生士が出向いて指導しています。
また、2019年4月に「認知症ケアチーム」が新たに発足しました。身体疾患で一般病棟に入院された認知症の患者さんに対し、精神科医や看護師などが連携してご本人やご家族のケアにあたっています。

チームの中核を担う人材育成の取り組み
チーム医療の取り組みは、一人ひとりの医療スタッフの専門性の高さに支えられています。兵庫医科大学病院では、2018年度から特定行為研修を修了した看護師を配置し、2024年3月現在、10名の特定行為看護師が在籍しています。これは、ある特定の医療行為を委員会で作成した手順書を基に実施できる、非常に高い専門知識と技術を有した看護師です。特定行為研修を修了した看護師は、患者さんの病態の把握や観察の注意点を病棟看護師と共有し、錬度の高い連携をすることで、より安全で質の高い看護を提供しています。
また、今年度より医師の働き方改革が実行されます。医師の労働時間の短縮のためには医療スタッフへのタスクシフトも重要です。このタスクシフトに特定行為看護師と認定看護師は重要な役割を果たします。本学の看護師特定行為研修課程と認定看護師教育課程は他施設にも門戸を開いており、地域の医療機関の医師の働き方改革にも貢献したいと考えています。
チーム医療の今後の課題
チーム医療はその数を増やしただけでは意味がなく、今後はチーム医療の評価も重要になってきます。実際には、1)医療の質:合併症は減少しているのか。早期社会復帰はできるようになったのか。2)経済的視点:費用対効果は期待できるのか。3)患者さんの視点:患者さんの満足度は向上しているのか。4)職員の視点:職員の負担軽減効果はどうか。などが評価項目となります。この点についても今後検討していきたいと考えています。
安心して治療に専念していただくために
わたし自身、医療事故を未然に防ぐ取り組みや、実際の医療事故に対する対策を検討する医療安全管理責任者を2年間務めました。これも、さまざまな診療科の医師や看護師、薬剤師、職員などで構成されている、兵庫医科大学病院に不可欠な医療チームです。安全で質の高い医療が提供できるよう、今後も努めてまいります。
兵庫医科大学病院では今後、チーム医療体制をますます推進し、患者さんとご家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を高め、安心・安全な医療を提供してまいります。
※最新更新日 2024年4月1日
●関連リンク
チーム医療の紹介

いけうち ひろき 池内 浩基 病院長
- 専門分野
-
- 炎症性腸疾患の外科治療
- 資格等
-
- 日本外科学会 専門医・指導医・代議員
- 日本消化器外科学会 専門医・指導医・評議員
- 日本大腸肛門病学会 専門医・指導医・評議員
- 日本消化器病学会 専門医・指導医・財団評議員
- 日本消化管学会 専門医・指導医・代議員・理事
- 日本炎症性腸疾患学会 専門医・指導医・理事
- 日本腹部救急医学会 専門医・教育医・評議員
- アジア炎症性腸疾患機構 監事
- 厚労省難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班 班員
- 医学博士
その他の取り組み