診療科について
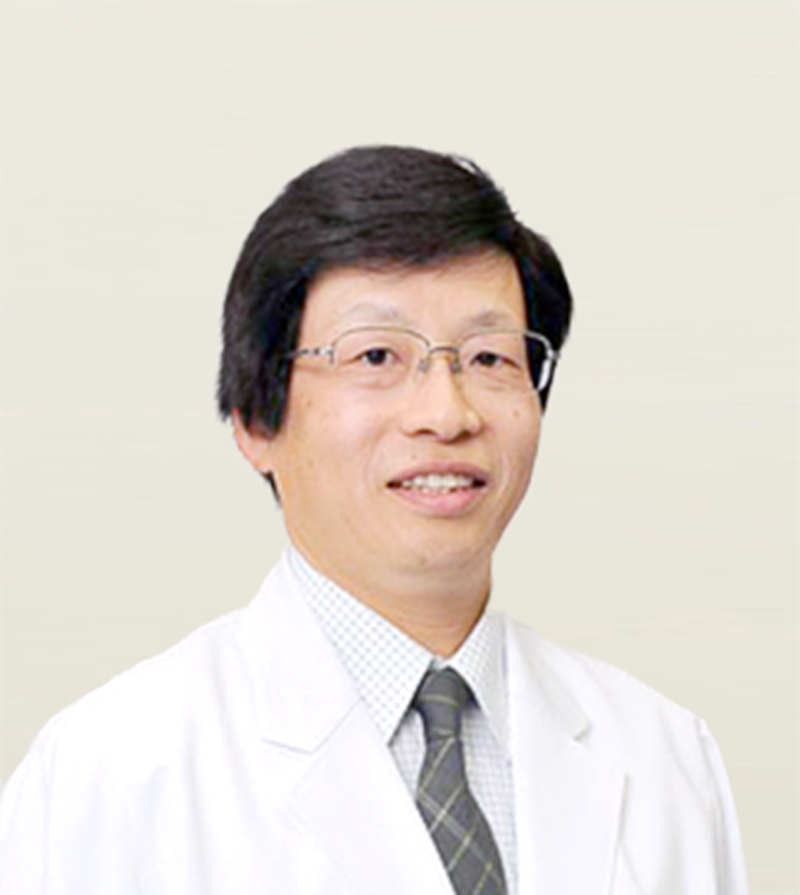
ご挨拶
小山 英則 (こやま ひでのり) 診療部長
診療体制
日本糖尿病学会専門医9名、日本内分泌学会専門医4名、日本動脈硬化学会専門医2名など、高度な専門知識と経験を有する総勢22名(大学院生、レジデントを含む)で、年間のべ約31,000名の外来患者さん、手術前後の管理も含めて約1,500名の入院患者さんに対応しています。
また、糖尿病認定看護師、療養指導士、栄養士、薬剤師とともに、病気の管理をサポートします。
高度な専門医療
【糖尿病診療】
1.糖尿病患者さんの認知症や心筋梗塞、脳梗塞などの予防法を提案します。
2.インスリンポンプや持続血糖モニターなどを用いた最先端の糖尿病診療を行います。
3.糖尿病患者さんの意識障害など、救急の合併症に対応します。
4.インターネット(IoT)を用いた糖尿病療養指導に取り組んでいます。
5.重症肥満に対する減量手術を提案・管理します。
【内分泌・代謝診療】
1.重症の高血圧にひそむ内分泌の病気を診断・治療します。
2.副腎の腫瘍を適切に診断・治療します。病状によっては手術だけでなく、ラジオ波による治療も可能です。
3.脳下垂体の腫瘍を適切に診断・治療します。
4.低カリウム血症、低ナトリウム血症などにひそむ病気を診断・治療します。
5.高カルシウム血症、低カルシウム血症などの原因を調べて、適切に治療します。
6.甲状腺の腫瘍が、がんかどうか診断し、治療方針を提案します。
7.コレステロールが非常に高くなる家族性高コレステロール血症を遺伝子診断などを通じて適切に診断・治療します。
8.痛風による重症の関節炎を適切に治療します。
9.睡眠時無呼吸症候群の診断とCPAPなどによる治療を行います。
主な検査・設備
インスリンポンプ
インスリンポンプ療法は、携帯型のインスリンポンプを用いてインスリンを注入する治療法です。時間帯ごとに基礎インスリン注入量をきめ細やかに設定できるため、低血糖を避けつつ、血糖管理が改善することが期待されます。また、インスリン注入に関するさまざまな便利な機能を使用することができ、患者さんの生活に合わせたインスリン投与を行うことができます。
持続血糖モニター
持続血糖モニターは、皮下組織間液中の糖濃度を連続的に測定し、患者さんの日々の血糖変動を詳しく調べる検査です。これによって、食後高血糖や夜間の低血糖などを正確に評価することができ、治療方針の調整に利用することができます。また、患者さん自身がご自身でリアルタイムの血糖値や血糖値の変化について評価し、自己管理に使用するタイプ(リアルタイムCGM)もあります。
血管内皮機能検査
血管内皮機能検査として、当院ではFMD(血流依存性血管拡張反応)検査を行うことができます。本検査では上腕にマンシェットを用いて駆血し、駆血前後の血管の広がりやすさを超音波装置を用いて測定します。血管内皮機能低下は動脈硬化の初期段階で生じることが知られており、血管内皮機能を評価することは非常に重要です。
頚動脈エコー
超音波を用いて首の血管の動脈硬化の状態を評価します。血管が塞がっていることが見つかることもあります。現状の動脈硬化を把握することで、生活習慣の改善や治療の強化につなげることができます。
遺伝子検査
遺伝子検査とは、病気の診断をしたり、薬の効き具合を予測するために遺伝子を調べることをいいます。遺伝子は親から子へ引き継がれるものです。当科では主に血液を用いて検査を行います。家族性高コレステロール血症など、多くの遺伝子の病気の診断を行っています。
副腎腫瘍ラジオ波焼灼術
当院では副腎腫瘍のうち、一部のホルモンを過剰に分泌する腫瘍に対する治療として、放射線科と協力してラジオ波焼灼術を行っています。経皮的に電極針を腫瘍に挿入し、電流を流すことによって発生した熱で病変を固めてしまう治療法です。
CPAP
重症の睡眠時無呼吸症候群と診断されたときに行う治療法です。睡眠中に酸素を送り込むことにより、気道が塞がるのを防ぎます。
甲状腺生検
甲状腺腫瘍の良性・悪性の区別をつけることが主な目的です。採血に用いるのと同じ太さの針を甲状腺に刺して、注射器で細胞を吸い込み、針の中に留まった細胞をみて診断します。採血するのと変わらないくらいの侵襲で、外来で簡単に何度もできる検査です。
主な対象疾患と診療内容
1型糖尿病
インスリン分泌が高度に低下した1型糖尿病患者さんにおいてはインスリンによる加療が不可欠となります。当院では、インスリンの自己注射およびインスリンポンプ療法を行うことができます。さらに、インスリンポンプ療法の中でも、持続血糖モニター機能をもったインスリンポンプを用いて血糖管理を行うSAP療法を積極的に行っています。
2型糖尿病
肥満や運動不足等のために血糖値を下げるホルモンであるインスリンの作用が弱くなり、高い血糖値が持続する状態です。血糖値が多少高くても自覚症状は全くありませんが、網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化症といった合併症が静かに進行します。合併症が進行するとさまざまな自覚症状が出てきますが、そこから元に戻すことは難しいため、早期発見し早期治療が必要な病気です。血糖値を良好に保つことで上記の合併症の進行を抑えることができます。治療法には食事療法、運動療法、薬物療法(内服、注射)があり、特に食事・運動療法が重要です。当院では、多くの合併症に関連する検査を行いながら、患者さんの病状にあわせた最適な生活習慣指導・薬物療法を提案します。
妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠
糖代謝異常妊娠の患者さんに対しては、食事療法などの生活指導を行い、必要に応じてインスリン治療を行います。内科だけではなく、産科婦人科、小児科、臨床栄養部などとも密に連携を取りながら、患者さんごとに治療方針を決定し、安心して出産にいどんでいただけるよう取り組んでいます。
低血糖症
低血糖症の多くは糖尿病薬物治療の副作用として現れることが多く、糖尿病の薬物治療を受けておられる方は低血糖に対する注意が必要です。適切に対応できれば過度に恐れる必要はありませんので、合併症を予防する観点からも高血糖を放置することは避けたいものです。低血糖を恐れすぎると高血糖が続きますし、治療を強めると低血糖の可能性があがることがあるため、この両者のバランスをとることが糖尿病治療の難しい点です。当院では、さまざまな先端技術を用いて、このバランスをベストに近づける方策を提案します。また、糖尿病の方以外にも、インスリノーマ(膵臓の腫瘍)など低血糖の原因は多数存在します。当院では、先端の技術を駆使して、原因を探ります。
下垂体腫瘍
脳下垂体にできる腫瘍は特定のホルモンを産生することが多く、そのホルモンの種類によって多彩な症状を呈します。産生しているホルモンを負荷試験によって調べて、MRIを用いて腫瘍のサイズや位置を把握します。その後、脳神経外科と協力し、手術あるいは薬による治療で腫瘍の根治をめざします。
下垂体機能亢進症
負荷試験などにより、過剰になっているホルモンを鑑別し、手術あるいは薬による治療で、ホルモンの過剰を是正します。
下垂体機能低下症
機能検査によって、産生が低下しているホルモンを鑑別し、薬による適切な補充によってホルモンの機能を補います。
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンが高くなる病気の代表疾患はバセドウ病ですが、その中には甲状腺に炎症を起こして甲状腺ホルモンが血液に漏れ出す病気(無痛性甲状腺炎や亜急性甲状腺炎)が混じっています。特に無痛性甲状腺炎は痛みがないため、バセドウ病との区別が難しいのですが、両者の治療法は全く異なりますので、正確な診断が重要です。
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンが低下する病気の代表は橋本病ですが、橋本病は甲状腺機能が全く正常な状態から、重症の機能低下症までさまざまです。その機能低下の程度に合わせて甲状腺ホルモン補充療法を行います。また妊婦さんに関しましては、流産・早産予防のために軽い甲状腺機能低下症の時も、甲状腺ホルモン補充療法を行うことがあります。
甲状腺腫瘍(がんを含む)
甲状腺の腫瘍には良性のものと悪性のものがあります。甲状腺超音波検査、甲状腺穿刺吸引細胞診や種々の画像診断を用いて、検査を進めます。
副甲状腺機能亢進症
血液中のカルシウムが増加する病気です。首の甲状腺の裏にある副甲状腺という小さな腺が腫瘍などで腫れて、副甲状腺ホルモンが過剰につくられます。腫瘍とホルモンが過剰につくられている部位を特定し、外科と協力し、手術あるいは薬による治療で、カルシウムを是正します。
副甲状腺機能低下症
血液中のカルシウムが、副甲状腺ホルモンが不足することにより低下する病気です。負荷試験などによって、副甲状腺ホルモンの低下の原因を調べて、薬による治療でカルシウムの低下を是正します。
骨粗しょう症
骨がもろくなる病気で、背骨の圧迫骨折などを起こします。X線を用いて骨密度の評価を行い、原因を特定した上で、骨密度を上昇させる最適な治療薬の選択を行います。
原発性アルドステロン症
副腎からアルドステロンというホルモンが過剰に分泌されることにより、高血圧や血液中のカリウム濃度の低下を引き起こす病気で、脳卒中や心不全などの一因となることもあります。内服や手術、ラジオ波焼灼術で治療を行います。治療により降圧薬の減量や中止ができる可能性があります。
クッシング症候群
副腎からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌されることにより、高血糖や高血圧、肥満などを引き起こす病気です。手術やラジオ波焼灼術、内服により治療を行います。
褐色細胞腫
アドレナリンが不必要に分泌される病気で、動悸や発汗、頭痛、高血圧、糖尿病の原因となります。血液・尿検査、画像検査で診断し、手術や薬物治療を行います。
副腎腫瘍(がんを含む)
副腎にできる腫瘍は良性腫瘍やがん、血管腫など様々な種類のものがあります。良性の腫瘍でも、副腎のホルモンを過剰に分泌するものもあり、手術が必要となることがあります。血液・尿検査や画像検査で診断を行います。
副腎皮質機能低下症
副腎が分泌するホルモンが不足することにより、疲れや食欲低下、低ナトリウム血症、血圧低下、意識障害などを引き起こす病気です。典型的な症状がないため、なかなか診断がつかないことも多い病気です。適切に診断し、ホルモンの補充療法を行います。
低ナトリウム血症
血液中のナトリウム濃度が低下すると、疲れ、ふらつき、食欲低下、意識障害などの症状を引き起こすことがあります。がんが原因で起こることもあり、ナトリウム濃度が低下している原因を調べ、適切に治療を行います。
低カリウム血症
血液中のカリウム濃度が低下すると、筋力の低下や不整脈などを引き起こすことがあります。カリウム濃度が低下している原因を調べ、適切に治療を行います。
重症高血圧(内分泌高血圧など)
たくさんの降圧薬を服用しても血圧が高い方や、若い頃から血圧が高い方はホルモン異常が高血圧の原因(内分泌性高血圧)の可能性があります。ホルモンの異常がないか血液や尿検査などで検査を行います。原因によって内服、手術、ラジオ波焼灼術など適切な治療を行います。
重症肥満
重度肥満患者さんにおいて、その他の病気によって引き起こされた肥満かを内分泌的検査(血液・尿検査、画像検査など)で検査を行っています。当院では、外科と協力して、肥満減量手術も実施しています。
痛風・高尿酸血症
痛風発作は中年男性に好発しますが、痛風・高尿酸血症治療の一番の問題点は関節の痛みがなくなると通院を自己中断してしまうことです。痛風をお持ちの方は、血液中に溶けきらない尿酸塩結晶が長年にわたり少しずつ関節に蓄積している状態ですので、痛みを抑えるだけでは治療としては不十分です。血中の尿酸値をよい値に長期間維持することでようやく痛風関節炎の発作回数は減少していきます。また、高尿酸血症は生活習慣病のひとつであり、心臓や腎臓の病気の原因になることがあります。当院では、合併症も考慮した治療をお手伝いします。
脂質異常症
コレステロールや中性脂肪が血液中に増加する病気です。心筋梗塞などの動脈硬化を引き起こします。原因検索と併せて、頸動脈超音波検査や動脈脈波伝播速度検査などを用いた動脈硬化の評価も行います。生活習慣のアドバイスや薬によってコレステロール、中性脂肪の低下をめざします。
家族性高コレステロール血症
血液中のコレステロールが非常に高くなる遺伝子病です。遺伝子検査なども含めた精密検査を行い診断しています。通常の治療薬では改善しない方には、最新の治療薬を用いた高度医療を提供しています。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に気道が塞がってしまうことにより、呼吸が止まる病気です。睡眠が障害されますので、重症の方は昼間の眠気などの症状が出ますが、自覚症状のない方が多いです。睡眠中に交感神経の緊張をおこし、高血圧の原因になる他、心筋梗塞などが起こりやすいことも知られています。重症と診断されれば、CPAPという治療の適応になります。
診療実績
2023年の診療実績
| 糖尿病 | 1型糖尿病 | 20 |
|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 239 | |
| インスリノーマを含む低血糖 | 4 | |
| 脳下垂体疾患 | 下垂体機能低下症を含む下垂体機能検査実施症例 | 37 |
| クッシング病 | 1 | |
| 尿崩症 | 4 | |
| 下垂体腫瘍精査及びプロラクチノーマ | 4 | |
| 甲状腺疾患 | 機能低下症 | 12 |
| Basedow病 | 7 | |
| 甲状腺クリーゼ | 1 | |
| カルシウム代謝異常 | 原発性副甲状腺機能亢進症を含む高カルシウム血症精査 | 18 |
| FGF23産生腫瘍精査を含む低リン血症及び骨軟化症 | 4 | |
| 副腎疾患 | 原発性アルドステロン症 | 33 |
| クッシング症候群 | 10 | |
| 褐色細胞腫 | 13 | |
| 二次性高血圧精査 | 16 | |
| 副腎皮質機能低下症 | 40 | |
| 非機能性副腎腫瘍 | 37 | |
| 副腎癌 | 4 | |
| 電解質代謝異常(SIADHなど) | 9 | |
| 脂質異常症 | 5 | |
| 高度肥満症精査及び術後フォロー | 19 |
2022年の診療実績
| 糖尿病 | 263 | |
|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 23 | |
| 2型糖尿病 | 217 | |
| その他の糖尿病 | 7 | |
| 高度肥満 | 16 | |
| 低血糖 | 10 | |
| 脳下垂体疾患 | 40 | |
| 下垂体機能低下症 | 26 | |
| 先端巨大症 | 1 | |
| クッシング病 | 5 | |
| 尿崩症 | 6 | |
| プロラクチノーマ | 2 | |
| 甲状腺疾患 | 16 | |
| 機能低下症 | 9 | |
| 甲状腺腫瘍 | 2 | |
| Basedow病 | 5 | |
| カルシウム代謝異常 | 10 | |
| 副甲状腺機能亢進症 | 8 | |
| 副甲状腺機能低下症 | 1 | |
| ビタミンD欠乏症 | 1 | |
| 副腎疾患 | 109 | |
| 原発性アルドステロン症 | 30 | |
| クッシング症候群 | 13 | |
| 褐色細胞腫 | 10 | |
| 副腎皮質機能低下症 | 21 | |
| 非機能性副腎腫瘍 | 32 | |
| 副腎癌 | 3 | |
| その他 | 電解質代謝異常(SIADH、Gitelman症候群など) | 11 |
| 二次性高血圧精査 | 13 | |
| 脂質異常症(家族性高コレステロール血症など) | 3 | |
| 痛風・高尿酸血症 | 1 | |
| その他 | 20 |
2021年の診療実績
| 糖尿病 | 241 | |
|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 22 | |
| 2型糖尿病 | 194 | |
| その他の糖尿病 | 6 | |
| 高度肥満 | 19 | |
| 低血糖 | 9 | |
| 脳下垂体疾患 | 54 | |
| 下垂体機能低下症 | 43 | |
| 先端巨大症 | 2 | |
| クッシング病 | 0 | |
| 尿崩症 | 8 | |
| プロラクチノーマ | 1 | |
| 甲状腺疾患 | 20 | |
| 機能低下症 | 12 | |
| 甲状腺腫瘍 | 2 | |
| Basedow病 | 6 | |
| カルシウム代謝異常 | 24 | |
| 副甲状腺機能亢進症 | 22 | |
| 副甲状腺機能低下症 | 1 | |
| ビタミンD欠乏症 | 1 | |
| 副腎疾患 | 147 | |
| 原発性アルドステロン症 | 44 | |
| クッシング症候群 | 8 | |
| 褐色細胞腫 | 10 | |
| 副腎皮質機能低下症 | 34 | |
| 非機能性副腎腫瘍 | 51 | |
| その他 | 電解質代謝異常(SIADH、Gitelman症候群など) | 21 |
| 二次性高血圧精査 | 14 | |
| 副腎癌 | 1 | |
| 脂質異常症(家族性高コレステロール血症など) | 9 | |
| 痛風・高尿酸血症 | 3 | |
| その他 | 12 |


