心臓弁膜症
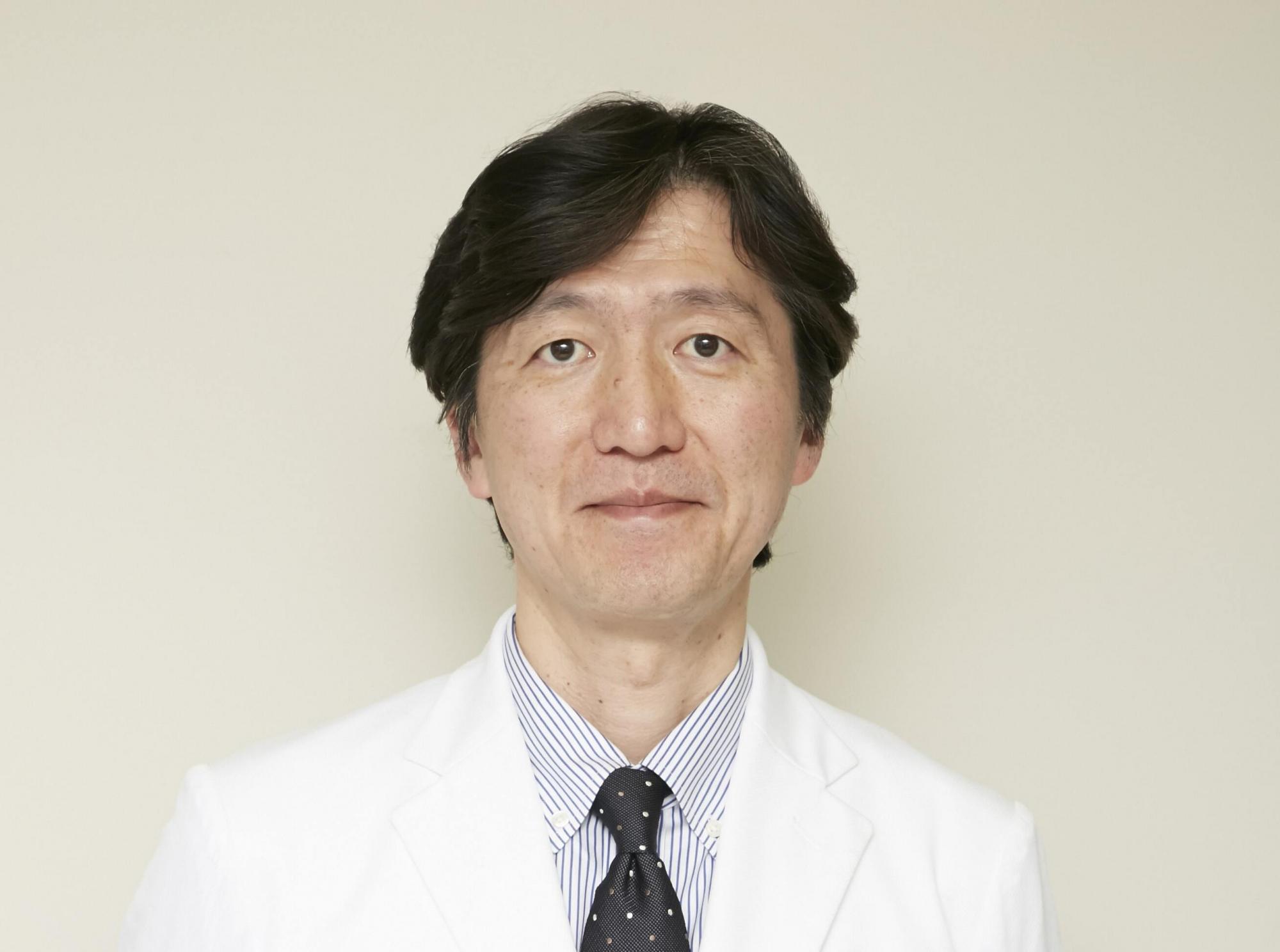
1日に約10万回も拍動し、全身に血液を送り続けている心臓。心臓弁の機能が悪くなり、心臓内で正常に血液が流れなくなるのが心臓弁膜症です。
「心臓弁膜症」って、どんな病気?
心臓には4つの弁がある
心臓には4つの部屋があり、血液が一方向に流れるよう、それぞれに弁があります。
血液が正常に流れなくなります
弁がきちんと閉まらず血液が逆流する閉鎖不全症(逆流症)、開きにくくなって血液の流れが滞る狭窄症の2つがあります。
多くは心臓の左側で起こる
弁膜症の治療が必要になるのは、ほとんどが左側の僧帽弁と大動脈弁です。
症状が出るのは心臓が弱ってから
心臓はなかなかへこたれない臓器。動悸や息切れ、足のむくみなどの症状が出るのは病状が進行してからです。
誰でもなりうる病気
原因は、加齢による変性・硬化や動脈硬化症、リウマチ熱、歯科治療等に端を発する感染症などさまざま。
患者さんの体にやさしく
手術の選択肢も増えてきた「心臓弁膜症」の治療
心臓弁膜症の治療について、低侵襲な心臓手術のスペシャリストである心臓血管外科の先生に話を聞きました。

心臓血管外科 主任教授 坂口 太一
MICS手術の執刀経験は、日本でもトップクラスです。
患者さんの年齢やライフスタイルも考慮しながら、チーム医療を行っています。
心臓弁膜症には、弁が開きにくくなることで起こる狭窄症と、きちんと閉じなくなり逆流が生じる閉鎖不全症(逆流症)があります。軽症の場合は経過観察をしたり、薬によって症状の緩和を図ったりしますが、根本治療は手術しかなく、最適な手術時期や方法を循環器内科と連携して決めています。近年は手術の低侵襲化が進み、患者さんの体への負担が小さくなっており、術後の回復がより見込める早期のうちに手術をすることも増えています。
手術には、弁を温存したまま修復する弁形成術と、人工弁に置き換える弁置換術があります。僧帽弁の閉鎖不全症に対しては、兵庫医科大学病院では9割以上で弁形成術を行っています。狭窄症では、基本的に弁置換術を選択します。人工弁には機械弁と生体弁の2種類があり、機械弁は耐久性では優れますが、血を固まりにくくする薬を生涯にわたって飲み続ける必要があります。生体弁では必ずしもその必要はないものの、耐久性に劣る面があるため、人工弁を選択する際には患者さんの年齢や生活を十分に考慮します。
近年、3D内視鏡を使用して行う「MICS(ミックス)」という手術が保険診療で行えるようになりました。胸骨を切ることなく小さな傷で済むので、出血や感染症のリスクが低い上、術後の運動制限もありません。MICS手術については、私自身がこれまで500例を超える手術を行ってきており、兵庫医科大学病院は国内トップクラスの施設として手術見学を受け入れるなど、安全かつ質の高い技術の普及にも努めています。また、大動脈弁狭窄症に対しては、カテーテルを使って弁を置き換える「TAVI(タビ)」という手術があり、リスクが高い患者さんにも、より安全に手術を受けていただくことができるようになっています。
患者さんのQOL(生活の質)を保つ・上げることを何より大切に、当院では、心臓血管外科・循環器内科・麻酔科等でハートチームを結成してTAVI手術に取り組むなど診療科を超えて連携しつつ治療を進めています。
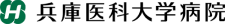

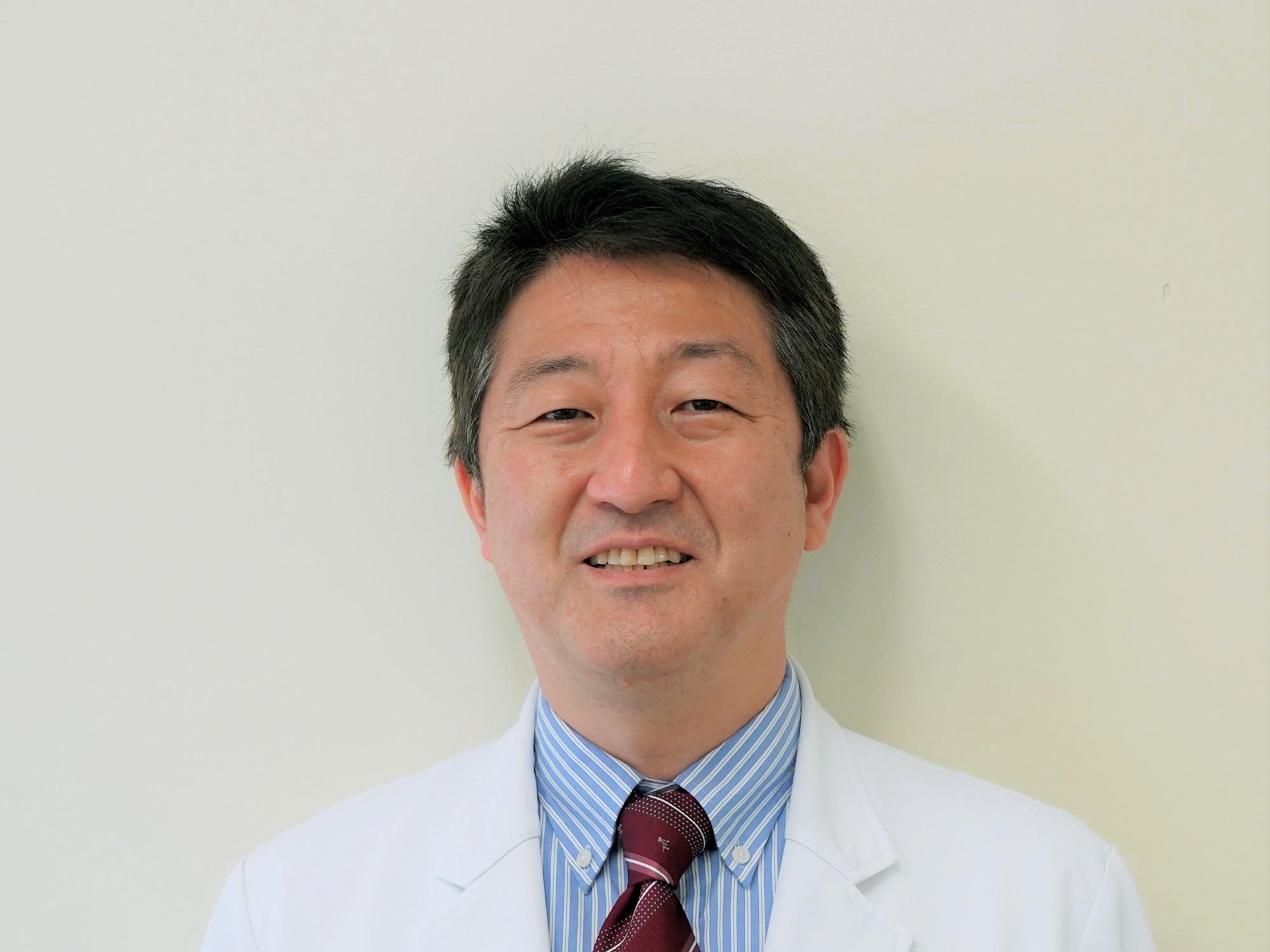
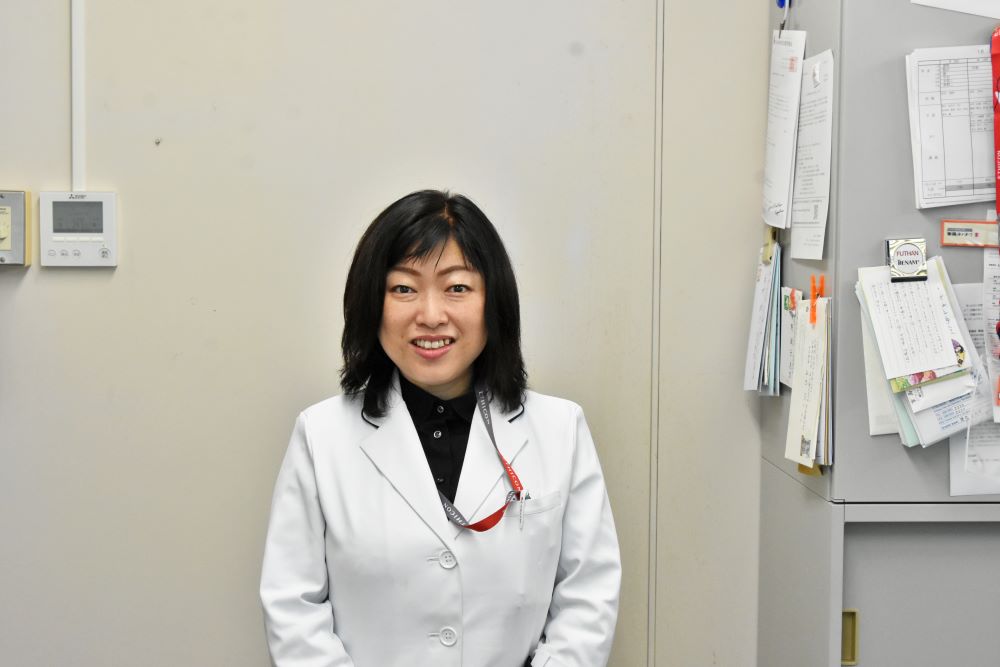
.jpg)